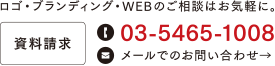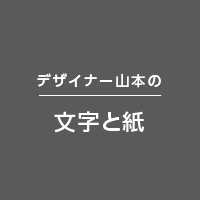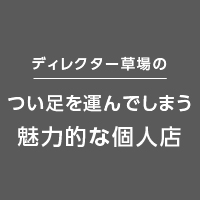こんにちは!デザイナーの山本です。
コロナウィルスの影響で、弊社も在宅勤務となり、
家という環境を仕事場にもできるように日々奮闘しております。
外出は中々できませんが、
自炊を毎食するため、ご飯をよく炊いて、
バランスを考えるようになり、
レシピブックを取り出して作るようになりました(笑)
健康に気をつけつつ、今しかできないことを見つけて、
お家生活も楽しみながら過ごしたいです。
オンラインでの生活が必須になってきているタイミングですが、
今回は、「紙の歴史」について書きたいと思います。
紙ができるまで
BC3000年代からAD1000年まで古代エジプト文明において、
水草パピルスの茎から皮をはぎ、
茎の中心部にある髄(芯)を薄く切ったものを材料とした
「パピルス」がエジプトを中心に使用されていました。
また、紀元前2世紀あたりでは、
発明された羊皮紙(パーチメント)が書写材料として普及しました。
主にヨーロッパで使われていましたが、非常に高価だったので、
紙の普及とともに使用されなくなったそうです。
紙はいつできたの?
紙は、紀元前2世紀頃、中国で発明されたと考えられています。
西暦105年頃に蔡倫(さいりん)という
後漢時代の役人が行った製紙法の改良により、
使いやすい実用的な紙がたくさん作られるようになったと言われています。
ちなみに蔡倫が紙作りに使った材料は、
麻のボロきれや、樹皮などでした。
紙の発展
その後、紙の材料や製造法は改良を重ねられながら、
絹の伝播(シルクロード)と同様に、西洋へと伝えられていきました。
8世紀頃にアラビアに、
そして10世紀頃にはエジプトでパピルスに代わって普及、
12世紀には地中海を経由して製紙技術がヨーロッパに伝わり、
製紙工場がスペインやフランスなど各地につくられました。
15世紀にはヨーロッパ全土に広がり、
アメリカでは1690年に初めてフィラデルフィアに製紙工場がつくられます。
日本へ紙が来たのは…?
日本で紙がつくられるようになったのは
仏教をはじめ、大陸の文化や技術の交流が盛んになった
5~6世紀頃だと考えられています。
日本では9世紀初頭に確立したとされる流し梳きによる薄手の紙が、
楮や雁皮などをおもな原料として製造されていました。
日本の和紙の製造は、
原料をはじめその工程には紙質を良くするための
さまざまな工夫や改良が加えられてきましたが、
工程の機械化はされず、
近代に西洋から洋紙の製紙技術が導入されるまで、
主に人の手によって行われていました。
日本での広がり
開国まもなく、明治5年〜8年頃、製紙会社によって、
紙の操業が始まったそうです。
意外と近代ですね…!
日本の洋紙産業は文明開化とともにスタートしました。
以降、ヨーロッパで発明された近代的な技術を次々と取り入れ、
発展していきました。
また、明治から大正にかけては、
新聞・雑誌・書籍などに使われる紙の需要も拡大。
それにより製紙産業が発展していったということです。
紙の発展はパピルスから考えるととても長くかかっていますが、
記録するということが文明の発達ともに発展してきたことがわかります。
(デジタル社会の発展は、よりめざましいですね…!)
最近はオンラインで、デジタルばかりなので、
個人的にはとてもアナログな紙が恋しくなる今日この頃です。
お家で読書も楽しみつつ、この時期を乗り切りましょう〜!