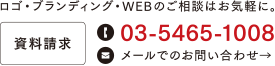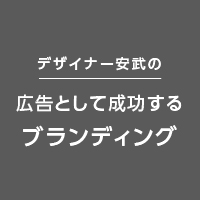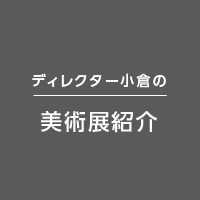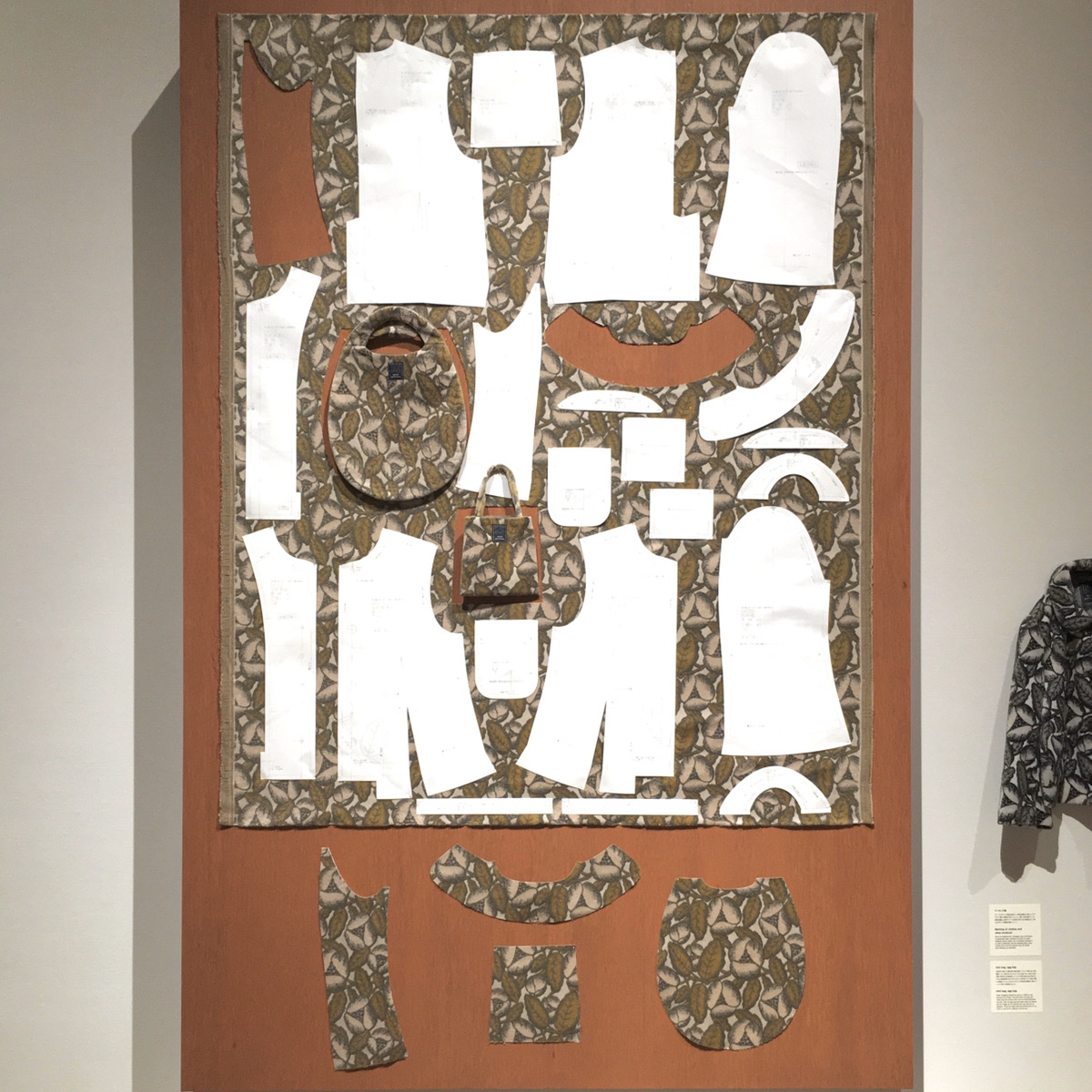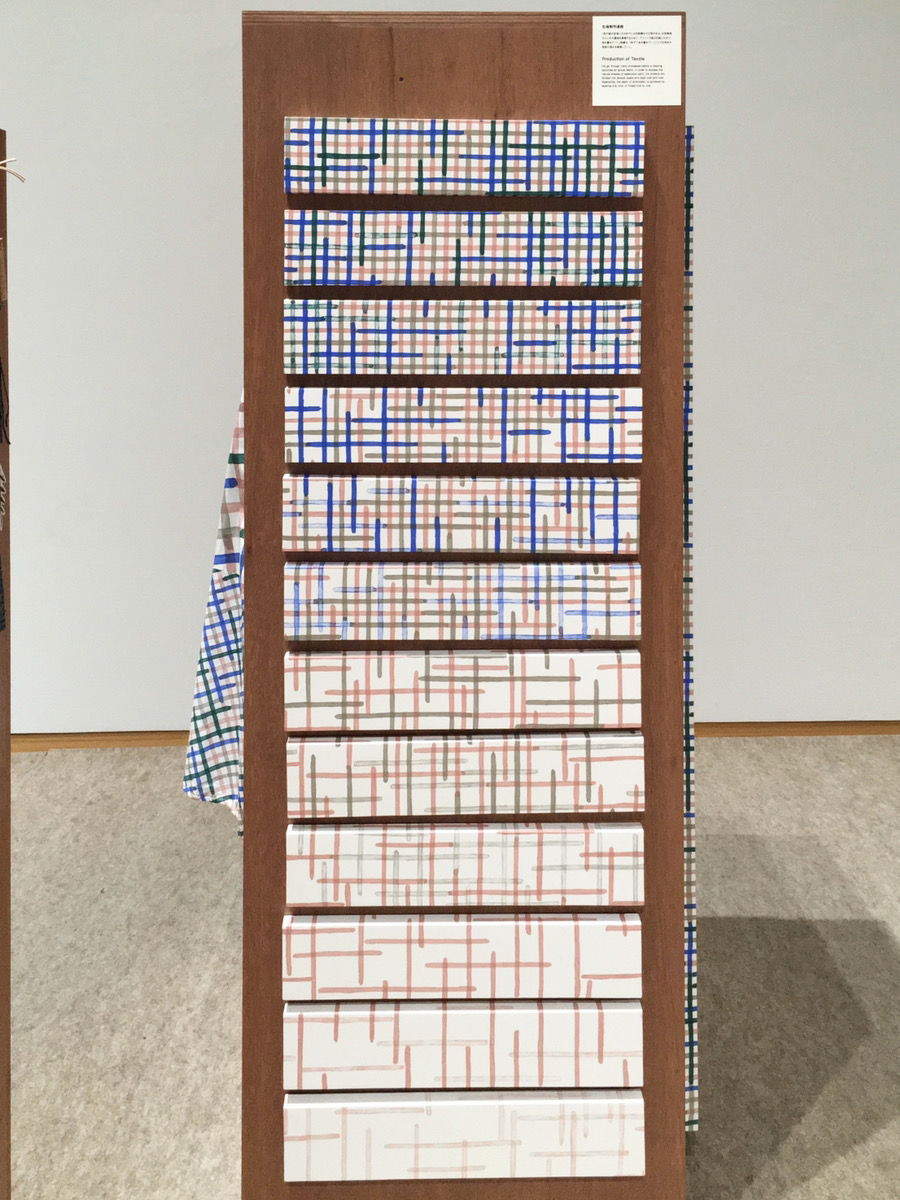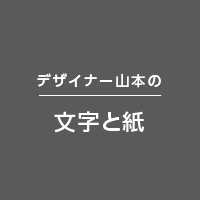こんにちは。デザイナー安武です。
1月もあっという間に最終週です。わが家の長男君が6歳の誕生日を迎え、私も母6歳か…と、しんみりではなく4月から小学生という不安の真っ只中におります汗
人生でなかなかのライフイベントですが、記憶には残るものなのでしょうかね?私は服装が地味だったことだけ覚えています。
さて、前回は「ブランディングを広告として見てみる」ということを書いてみました。
ちょっと時間が経ってあたらめて考えてみると、広告ってちょっと力業というか、受け手の吸収率や消化率を考えずに、驚きやインパクトをもって、強引に答えを決めてしまうようなところがあります。
ブランディングって、もっと受け手からのアプローチや、第三者の立場から、本当にあるべき姿を見つけていく、共創のイメージです。
広告がつくる流行
突然ですが、洗濯機の流行ってご存じですか?
縦型とかドラム式とかもありますが、今は「便利さ」ですかね。
洗剤をタンクにまとめて入れておいて、1回毎に量らないで済む。
スマホで洗濯がコントロール出来る。人に合わせて好みの洗濯が出来る。。
こんな便利機能が「今」の洗濯機。
これがたった5年ほど前は「清潔さ」が流行だったでしょうか。
世間があらゆる菌に敏感で、市場の多くが除菌殺菌に躍起になった頃の話。
さらに10年前は「省エネ」でしたかね。
こんなふうに広告によって、市場には大きく流行が生まれ、変わっていきます。
ブランディングとは、そのものの本質を正しく伝えるということ

洗濯日和ってこんな空でしょうか。。
ではところで、洗濯機の本質とは。
それはもちろん「キレイに洗ってくれること」ですよね。
でも今のご時世、忙しい中あらゆる洗濯物を、短い時間で水を無駄遣いせず、キレイに清潔に洗い上げ、部屋干ししても臭わず、家事分担もでき、メンテナンスも忘れず、インテリアとしてもかっこよく、もちろんコスパも求められる洗濯という家事のことを考えると、「キレイに洗います!」だけでは売れ残ってしまいますよね。
だからここで、「こんな機能もついていて、もちろんキレイに洗える洗濯機です」というアピールポイントが生まれるのです。
さてここでブランディングの目線です。
あれ?洗濯機のブランドってなんだろうか?と思いませんか。
本質を伝えるのがブランディングだとすると、洗濯の本質を伝えれば洗濯機のブランディングになるのか?といえば、それはなりませんよね。
日本の大手家電メーカーや海外メーカー、最近ではプロダクトメーカーや生活用品などの会社も家電をつくっています。
でもアピールされてる便利機能は、よく見たらA社もB社も一緒。
ではどんなところが違うのか。製品ではなくメーカーの違い。
その「違い」がブランド、という認識でしょうか。
丁寧に言えば、メーカーの製品にも複数のブランドがあったりしますが、製品によっては、メーカー=ブランドであったりもします。
ではブランディングをもしするならば、どんなふうになるでしょうか。
たとえば、「共働き等の忙しい家庭をサポートするための家電事業」だったり、
たとえば、「家電をインテリアにするデザイン家電メーカー」や、「もっとプロ仕様の高性能でタフな電化製品」など、いろいろ特色が出てきます。
これらが同様の機能で製品を売り出したとき、私たちはこのメーカーの考え方で見分けていきますよね。
ようやく出ました。
このメーカー(つくり手、売り手など)の『考え方』。
これがブランドの基礎なのではないでしょうか。
そして、この考え方というのは、流行によって変わるものではなく、経営理念であったり、社風や人柄といったものに近い、「アイデンティティ」と私たちが呼んでいるものの1つであると思っています。
それをブランディングのうえでは、正しく伝える「本質」とも言います。
洗濯機の話、いかがでしたか?
私じつはちょっとした洗濯機マニアみたいなもので…。
まだまだ洗濯機の話をしようと思えばできますが、それはまた別の機会に。
次回は、ブランドを決めるのは何か?という所を考えてみます。
2020年1月28日 | スタッフ:安武, 広告として成功するブランディング