Chapter5 吟味する
Lecture19 自分の100点は世間の60点
<POINT>
テストを受けたとき。提出する前にはもう一度見直すはずだ。モノづくりの工程も同じ。提出前に、もう一度見直して内容を磨くブラッシュアップを始めよう。
ついつい自分に甘い採点をしてしまうのはデザイナーの卵も同様で、「このデザインなら100点取れるでしょう!」と自信満々に出したものをボロボロにけなされる、なんてこともしょっちゅうです。
私も「自分の100点は、世間の60点」、こう自戒する日々です。
というのも、自分ではすばらしい完成度だと思ってしまう。一方で、60点だと思って見直してみると、つくっているときは気づかなかった穴や欠点を発見することもあるのです。
自分の仕事は60点の評価しか受けられないものだと自戒し、現状に満足しないことがとても大切になってきます。
もっと、わかりやすく伝えたい。
もっと楽しくて、もっと感動に満ちたものをつくりたい。
そんなモチベーションを消さずに残すためにも、60点の自戒は役立ちます。もちろん、自分が100点を取るべく全力を出したものを、60点だと思うことはつらく、きびしい。それでも、どうにかして1点でも2点でも多く引き上げていく。CHAPTER5はそんな磨きのステップです。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.146〜P.147
世の中、本当にいろいろな人がいます。境遇も価値観も考え方も様々です。
デザインエイエムでも、常に複数人の視点から物事を眺め、
俯瞰して考えることがもはや必須となっています。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
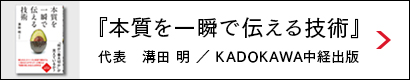 こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter4 つくる
Lecture18 「背景」でより魅力的にしよう
<POINT>
“どこにあるか” によって、物体の魅力度は大きく変わる。モノづくりの現場においても、「背景」をうまく使えば、魅力をアピールできる強力な武器となる。
最も身近で奥深い「余白」
「余白美」という言葉があります。
が、クライアントの中には、伝えたいことがたくさんあるばかりに、広告スペースの白い空間が無駄だと言う人もたまにいます。
しかし、闇があるから星の光が輝いて見えるように、黒があるから白が引き立ちます。
対象をより引き立たせるために、何もない、シンとした「余白」のスペースは絶対に必要なのです。
コンペスタイルのプレゼンの場で、他社に勝つためにただロゴを大きく目立たせようとする会社がたまにあります。他社より目立たねば、という気迫だけは伝わりますが残念ながら逆効果です。場所に適した声のボリュームがあるように、声を張り上げればその分うまく伝わるかというと、全然そんなことはありません。
また、ガヤガヤと騒々しい場所で、ひと言声を発しても、やっぱり誰も耳を傾けてはくれません。でも、ぴんと空気のはりつめた静かな中で、ポンと発する言葉は、否応なしに耳に入ってきます。
スピーチや会話のときも「間」の取り方が最も大事だと言われるように、声高にしゃべりまくるよりも、間を十分にとって発したひと言のほうが重みが出るのです。
余白は、無意味な空きではなく、わざと演出する「無空間」。
手を動かすときは、対象物だけを見るのではなく、背景の白い部分のバランスも同時に意識してみてください。そうすることで、より見やすく、美しいものができるはずです。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.128〜P.129
何もないスペースや静寂が存在すると、つい不安に感じてしまいがちですよね。
しかし、それらに確固たる理由があれば、そこに存在する場の力を必ず感じるはずです。
勇気をもって「余白」をつくってみましょう。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
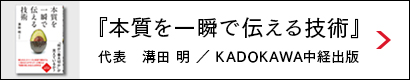 こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter4 つくる
Lecture17 ゼロからモノを生み出す技術
<POINT>
CHAPTER3「考える」で固めたアウトラインをもとに、細部をつくり込んでいこう。なぜそうするのかを常に考え、説明できるようにしながらつくるのがポイントだ。
設計図をもとに、細かいところに着手しよう!
CHAPTER4では、CHAPTER3「考える」で絞り込んだアイデアやラフ、構成案などをもとに、実際にモノをつくり出すステップに進みます。
使う素材や使い方は、すでに固めていますから、あとはがんばって手を動かすだけ。
迷うことなく、どんどん進めていきます。
とはいえ、すべてが予定どおりに進むとはかぎりません。家を建てる際も、綿密な設計図をもとに組み立て始めますが、いざ現場では数センチの誤差が生じるなど、臨機応変な調整がその時々で必要になります。
私たちのモノづくりにおいても、実際につくり始めてみると、「想像よりバランスが悪い」、「フォントが微妙に合ってない」、「解説の文字量が思ったより少し多かった」…など、予想外のアクシデントに見舞われることが多々あります。
でも、心配ありません。
完成予想図はすでに固まっていますから、そこに向けて調整しながら迷わず進めていけばいいのです。
もちろん、「この色がいい」「この言葉にしよう」とパッと判断しながら進めてかまいません。ただし、「なぜそう思うか」を考えておくことが大切です。説明できないならやめたほうがいい。デザイナーの感性に頼りすぎたものは、見る人の共感を得られません。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.121〜P.122
大工は家を建てるために、計算は必須ですよね。
きちんと理論立てて細部を作らないと、すぐ家も倒れてしまいますね。
一つ一つの取捨選択に対して「言語化」することを常に心がけたいです。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
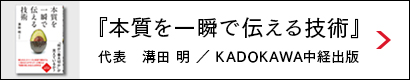 こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter3 考える
Lecture16 アイデアをどう絞り込むか
<POINT>
多くの選択肢が出揃ったら、次は、その中からベストなものを選びとる作業へ進む。
ここで選んだものが今後の骨組みとなり、方針となり、設計図となる。心して選ぼう!
「何をよしとするか」の軸足を定める
たくさんのアイデア(選択肢)が出揃ったら、次はベストなものを選びとるステップへと進みましょう。
せっかくいいアイデアが出ていても、選ぶものを間違えると台無しです。
ここは慎重にいきましょう。
とはいえ、たくさんあるものの中から、バシッとベストなものを選ぶというのも難しいもの。いったいどうすればいいのでしょうか?
ここで、ヨーロッパ人のカーテン選びを参考にしてみましょう。
カーテン売り場といえば、たとえば「赤」をひとつとっても、明るい赤やくすんだ赤、青みの強い赤、黄みの強い赤など、膨大な色数があります。
日本の場合、「インテリアに合う色はどれだろう」から始まって、「部屋に合うのはこれだけど、好みじゃない」「これを買ったら妻は何というだろうか」と続き、結局、「当店人気ナンバーワン」、もしくは「店長のオススメ!」を選ぶ――なんてことが少なくないようです。
一方、ヨーロッパ人の場合は、どんなに色数の多い売り場でも、自分が求めている色をパッと選べる人がとても多い。これができるのは、彼らが日頃から色に対して敏感であり、はっきりとポリシーを持っているから。
「インテリア」で選ぶのか、「今の気分」で選ぶのか。「何を基準に選ぶか」をはっきりと決めてのぞむことが大切なのです。
すなわち、何を一番よしとするのか。
誰にとっての“よし”か? 「本質を一瞬で伝える」という場面を考えたとき、それは自分ではありません。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.113〜P.114
例えば企画提案をするときも、お客さんの「課題」に対して解を選びます。
ここに提案側の個人的な好みは、あまり役に立たないでしょうね。
広い視野でコンセプチュアルに考える必要がありますね。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
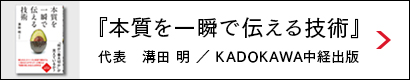 こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter3 考える
Lecture14 「伝わるアイデア」を生み出す5つのヒント
<POINT>
伝わるアイデア出しのための5つのヒントを紹介しよう。
効果は実証済み。真似する価値は大いにあるはずだ。
主役・脇役・エキストラをキャスティングする
主役・脇役・エキストラとは、みなさんもご存じのとおり、
舞台やドラマのキャストのことです。
・主役……ストーリーの主人公。最も目立たせたい人。
・脇役……主人公の魅力を存分に引き立てる役割。
・エキストラ……その他大勢。主役・脇役を引き立たせるための役割。
ミシュランで星を獲得した赤坂の中華レストランのロゴをつくった際は、
主役に店名を据えました。
次に、脇役とエキストラを考えていきます。
このときは、CHAPTER1、 CAPTER2で見いだした手掛かりの範囲の中で
考えるのがポイントです。
そこにないものを入れると、等身大の魅力ではなくなり、
本質から遠ざかってしまいます。
・主役……店名「Maison de YULONG(メゾン・ド・ユーロン)」
・脇役……イメージカラー「朱赤」
・エキストラ……店名を説明する文言「酒家 遊龍」
一方、資料作りなら、主役・脇役・エキストラはこんな感じになるかもしれません。
・主役……本題(出したい結論)
・脇役……本題へと誘導し、納得できる説得材料を示す文章
・エキストラ……読みやすいレイアウト、分かりやすい画像、文字組み
ここでは、大切なことや魅力的なことなど、「言いたいこと」を主役に据えます。
次に、その主役を引きたたせる脇役、エキストラを考えます。
いわば、「言いたいこと」がより効果的に伝わるように補強するイメージです。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.95〜P.96
主役を引き立てるように脇役を添える…まるでお花のブーケを作る時のようですね。
日頃の資料作りでも「一番言いたいことを大きく、他は小さく」を意識すると
見る側にとって分かりやすい資料となりますので、ぜひ実践してみてください。
また、今回事例に取りあげた「メゾン・ド・ユーロン」様は、
弊社WEBサイト内「WORKS」「お客さまの声」でもご紹介させていただいております。
こちらもぜひご覧くださいね。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
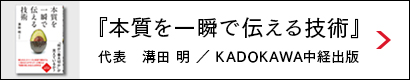 こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter3 考える
Lecture12 思考の「設計図」をつくる
<POINT>
全体を見たうえで、「伝えたい情報」「伝えなくていい情報」を決める。
これが「思考の設計図をつくる」という作業だ。
「言いたいこと」は極限まで絞る
CHAPTER1「よく見る」、CHAPTER2「受け止める」で、
対象をじっくり眺め、多くの手掛かりを集めました。
「受け止める」のステップでは、自己流の取捨選択を禁じましたが、
ここでは全体を見たうえで、「伝えたい情報」「伝えなくていい情報」を決めていきます。
というのも、細かいあれこれをゴチャゴチャと伝えても、受け手には届かないからです。
興味のない人や忙しい人にも一瞬で届くように、
「どうしても言いたい!」ことだけを整理し、厳選するのです。
このときの「どうしても言いたいこと」の数は、できる限り少なくするのが理想です。
ロゴのように一瞬で「らしさ」と「魅力」を届けたいもの、
あるいは長々と言葉で解説できない短時間のプレゼンなど、
解説の余地がないものほど、できるかぎり削ぎ落し、
一点集中で突破する。これが鉄則です。
さらに、その「どうしても言いたいこと」は、
ひと言で言えるくらい単純明快であることが大切です。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.83〜P.84
プレゼンでは1枚のシート上に1つの「キーワード」だけを載せたりしますよね。
喋りで詳細を補完しているうちに「どうしても言いたいこと」がぼやけてしまうため、
単純明快なワードを打ち出すことで、印象と記憶に、より強く残るんですね。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
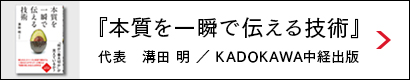 こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter2 受け止める
Lecture08 勝手に取捨選択をしない
<POINT>
ちゃんと得たはずの情報までかき消してしまうのが、主観という名の「色メガネ」。
このやっかいなメガネを外すには、自らの個性を消して“無”になることが大切。
あなたの「色メガネ」が情報をゆがめている
10ある情報が8になってしまう要因は、あと2つありましたね。
②10個の要素があることは知っていた。
が、そのうち2個は「重要じゃない」と判断して聞き逃した。
③10個の要素があることは知っていた。メモもとった。
が、そのうち2個は「重要じゃない」と思い、伝える際に省いた。
この問題は、どちらも本人が独断で「その話は重要じゃない」と判断したことです。
気持ちはわかります。打ち合わせの席で、余談に花が咲いてしまったり、
クライアントの話があまりにも長くて「もう何言ってんのかわかんない!」と思うことが、私も多々あります。
すると、だんだん疲れてきて、まず相手の言葉をメモするために
握ったペンを置いてしまいます。
「メモするのは、重要なことだけでいい」という心理が働きはじめるのです。
何が重要か、何が重要でないかを、自己流で判断してしまう。
ありがちですが、危険です。
いざ誰かにその内容を伝えようとしたとき、
「これは言わなくてもいいな」と勝手に判断してしまうのも同じです。
自己流で判断するということは、色メガネをかけた状態で判断するということです。
色メガネとは、「主観」や「個性」のこと。
主観や個性が強いと、客観性を失います。
だから、相手の言葉の意味をうがってとらえてしまったり、
重要度を汲み違えてしまったり、ということが起こるのです。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.59〜P.60
今回の話は、話す側の伝えるスキルも関係することですが、
聞く側も先方の話を歪めず、そのまま素直に受け止めることを意識したいですね。
今回取り上げたチャプターの全文や、その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
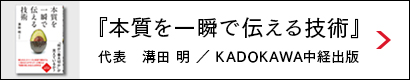 新年明けましておめでとうございます。
昨年はコロナによって、いい意味でも悪い意味でも、様々なことが変わった年でしたが、
今年も良い変化を起こしていけるように、弊社スタッフ共々頑張りたいと思います。
さて、こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
新年明けましておめでとうございます。
昨年はコロナによって、いい意味でも悪い意味でも、様々なことが変わった年でしたが、
今年も良い変化を起こしていけるように、弊社スタッフ共々頑張りたいと思います。
さて、こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter2 受け止める
Lecture06 「10を聞いて10を知る」を愚直に続ける
<POINT>
相手が話すことを、勝手に重要度を判断しながら聞いてはならない。
まずはいったん素直にすべてを聞くこと。
これが、本質を読み違えるミスを防ぐ第一歩だ。
10を聞いたのに8しか理解できない理由
さきほどの営業マンは、なぜ10を聞いたのに8しか渡せなかったのでしょう。
純粋な「聞き逃し」だったらまだいいのですが、
もしも次のような理由で「あえて」伝えなかったのだとしたら問題です。
①10個ある要素のうち、8個までは理解した。が、残りがイマイチ理解できなかった。
とはいえ、聞き直すのもはばかられた。まあニュアンスはつかんだと思った。
②10個の要素があることは知っていた。
が、そのうち2個は「重要じゃない」と判断して聞き逃した。
③10個の要素があることは知っていた。メモもとった。
が、そのうち2個は「重要じゃない」と思い、伝える際に省いた。
こうして、クライアントが伝えたはずの10個の要素のうち、2個が泡と消えたわけです。
これらはいずれも「受け止める」ことをしなかった、
いや、「受け止める」ことの大切さを知らなかったがゆえに招いた結果です。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.48〜P.50
この聞き逃した2個が、実は本質に関わる重要事項だったとしたら…ゾッとしますよね。
相手の方は「話を聞いてもらえていない!」と怒ってしまうかもしれません。
そうならないよう、しっかりと「10個」を聞き、「10個」であることを認識したいですね。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
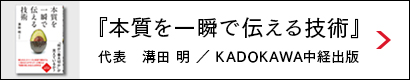 こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter1 よく見る
Lecture04 余計な「ノイズ」に惑わされるな
<POINT>
余計な感情のノイズを排除してこそ、質の高い仕事ができる。
「気遣い」「優しさ」「情け」も、ときに仕事をするうえでのノイズとなりうる。
「ノイズ」に気をとられると、ゴールを間違える
仕事はいろんな要素が複雑に絡み合っていますが、
「切り口」を設定したり、「なぜ?」と繰り返し問うことで「よく見る」ことができます。
仕事そのものをじっくり観察することによって、目的や課題などをあいまいにせず、
はっきりした形でとらえて進めることができるのです。
ただし、仕事を観察するとき、注意してほしいものがあります。
それは、「ノイズ」です。
直訳すれば「雑音」という意味です。
たとえば「保身を求める気持ち」「いい人だと思われたい気持ち」
「できる人だと思われたい気持ち」「あの人が好きだ・嫌いだという気持ち」
などがあります。
このノイズがあると、情報の本質を正しく読み取ったり、
伝えたりすることができなくなります。
目的、課題、手段……仕事を進めるうえで話し合うべきことはたくさんありますが、
ノイズがあると、言うべきことが言えなくなるのです。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.37〜P.38
日本人は察したり、控えめに表現することが多いかと思いますが、
仕事上では潔く「単刀直入」にはっきりと伝えることも、コミュニケーションの上では大事ですよね。
伝える時だけでなく、「聞く」時にも使えると思います。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
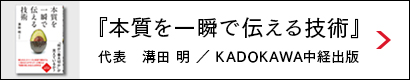 こんにちは、
アシスタントディレクターの小倉です。
少し前になりますが、三菱一号館美術館で開催中の「1894 Visions ルドン・ロートレック展」に行ってきました。
年代に焦点が当てられて、ルドンとロートレック以外にも様々な画家の作品を見ることができました。
こんにちは、
アシスタントディレクターの小倉です。
少し前になりますが、三菱一号館美術館で開催中の「1894 Visions ルドン・ロートレック展」に行ってきました。
年代に焦点が当てられて、ルドンとロートレック以外にも様々な画家の作品を見ることができました。
1894 Visions ルドン・ロートレック展
<展示概要> 開館10周年の最後を飾る本展覧会は、丸の内発のオフィスビルとして三菱一号館が竣工した年、「1894」年を軸に、当館のコレクションの中核をなす画家である、ルドンとトゥールーズ=ロートレックの時代に焦点を当てます。 1894年はルドンが色彩の作品を初めて発表した年であり、ロートレック、ルドン、ゴーガンが参加した「レスタンプ・オリジの刊行都市(1893-95)とも重なります。一方、同時代の日本では、フランスへ留学し、ルドンと同じ師のもとで学んだ山本芳翠が、代表作《浦島》を制作した時代でもありました。日本の洋画家と欧州の美術史の関係にも注目します。 本展は岐阜県美術館との共同企画であり、同館が誇る世界有数のルドン・コレクションから重要な木炭とパステル画、ゴーガンの多色刷えいの木版画を中心とした作品群、山本芳翠をはじめとる明治洋画の旗手たちの作品を出品します。国内外あわせて140点を超える作品で構成します。 (引用 1894 Visions ルドン・ロートレック展 チラシより) <印象に残った作品> ・山本芳翠「浦島」 昔話として馴染み深い浦島太郎をモチーフに描かれた作品です。 ※こちらのリンク先(チラシ2ページ目(PDF))に作品の画像が掲載されています。よろしければご覧ください。 竜宮城からの帰還の場面を描いていると思うのですが、 自分の知っている浦島太郎とは少し異なる部分があったり、異国の雰囲気を感じとても印象に残っています。 ・竜宮城が海の上に浮かんでいる ・後方に乙姫らしき人物も一緒についてきている ・竜宮城の人たちが身に着けている装飾に異国感を感じる など 山本芳翠が解釈した浦島太郎を見た感じです。 果たしてこれは帰還を描いているのか、浦島太郎は乙姫たちと別れて陸に戻るのか…想像が膨らむ作品でした。 このあと東京での展示が終了した後は、岐阜県美術館を巡回するようです。 三菱一号館美術館 1894 Visions ルドン・ロートレック展 2020/10/24(土)~2021/1/17(日) https://mimt.jp/visions/ 「本質を一瞬で伝える」とはどういうことか。 現在、世の中には本質を見抜くための技を伝授する書籍はたくさんあり、 様々な考え方や方法が紹介されていると思います。 しかし、見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。 そこで今回から全15回にわたり、弊社代表の溝田 明による著書 『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。 ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、 皆さまのビジネスにお役立てください。Chapter1 よく見る
Lecture03 「なんとなく」。このフワッとした気持ちを突き詰めろ
<POINT>
「なんとなく」という感覚的な言葉の中にも本質を読み解くカギがある。気持ちや願望もじっくり観察することで、想いの強さが見えてくる。
仕事は誰かの「願い」から始まる
仕事の現場でも、
「なんとなくこれがいい」
「うまく言えないけど、こうしたい」
こういう言葉を聞くことがあります。
そんなときも、「それはなぜ?」と聞き、突き詰めていくことで、理由や願いが明確な言葉になり始めます。
仕事は、誰かの「〇〇したい」という願いから始まります。
それは、クライアントの「企業イメージをアップしたい」だったり、上司の「商品開発のアイデアを出してくれ」だったり、同僚の「イベントの企画書づくり手伝って!」だったりします。
「なんとなく」ほどフワフワはしていませんが、「〇〇したい」という気持ちという意味では「ラーメンが食べたい」と同じなのです。
クライアントの願望に、「なぜ?」をぶつけることで、「安心して私たちの食品を口にしてほしいから」「使ってほしいから」など、「志」や「想い」に関する言葉もきっと出てくるはずです。
この「想い」の強さこそ、本質を見抜くときに注目すべき点なのです。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.33〜P.35
皆様いかがでしょうか。
「なんとなく」という気持ちについて自分で考えるだけでは、つい大したことがないのではと軽んじてしまいますよね。
しかし、私たちはその「なんとなく」に対して常に真摯に向き合い、きちんと整理をし、徐々に理由をはっきりとさせていきます。
そして最終的にはそれがずっと求めていたものだったということに気づくことできるのです。
これは決してデザインの世界だけでなく、様々な業界の仕事にも実践できるものではないでしょうか。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
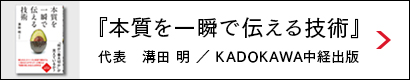 こんにちは
web担当の吉村です。
毎朝5時半に起きて朝活をしているのですが…
起きても真っ暗なので冬だなあ…と感じる毎日です。
朝はとくに寒いので、布団から出るのが惜しいですね…怠けないように続けていかなくては!
さて、今回は前回に引き続きSSL化の話題です。
前回は「常時SSL化とは何?」「しておかないとどうなるの?」にフォーカスしてお話させていただきましたが、実際に常時SSL化するためには何が必要なのかをまとめました。
(前回の記事はこちら)
こんにちは
web担当の吉村です。
毎朝5時半に起きて朝活をしているのですが…
起きても真っ暗なので冬だなあ…と感じる毎日です。
朝はとくに寒いので、布団から出るのが惜しいですね…怠けないように続けていかなくては!
さて、今回は前回に引き続きSSL化の話題です。
前回は「常時SSL化とは何?」「しておかないとどうなるの?」にフォーカスしてお話させていただきましたが、実際に常時SSL化するためには何が必要なのかをまとめました。
(前回の記事はこちら)

