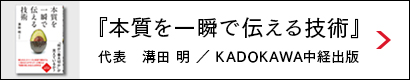オフィスに来られたことがある方はおわかりになるでしょうか。
弊社のオフィスは半地下となっており一日を通してあまり陽が入らないので、植物にとっては少し物足りない環境です。
そのため、日陰にもある程度強い植物を選ぶことにしました。
オフィスに来られたことがある方はおわかりになるでしょうか。
弊社のオフィスは半地下となっており一日を通してあまり陽が入らないので、植物にとっては少し物足りない環境です。
そのため、日陰にもある程度強い植物を選ぶことにしました。
 水やりは土の表面が乾いてきたら。また時々室内の換気も兼ねて空気を入れ替えることで病害虫の予防にもなります。私たちも同じ、換気を良くした方が健康に良いですよね。
ぜひ、今年は身近にグリーンを取り入れて、気分を上げてみてはいかがでしょう。
デザインエイエムスタッフのおすすめや最近気になっているモノ・コトなどをピックアップ!
定期的にご紹介してまいります!
今回の担当は、デザイナー安武です。
水やりは土の表面が乾いてきたら。また時々室内の換気も兼ねて空気を入れ替えることで病害虫の予防にもなります。私たちも同じ、換気を良くした方が健康に良いですよね。
ぜひ、今年は身近にグリーンを取り入れて、気分を上げてみてはいかがでしょう。
デザインエイエムスタッフのおすすめや最近気になっているモノ・コトなどをピックアップ!
定期的にご紹介してまいります!
今回の担当は、デザイナー安武です。
会社のすぐ近所にできたショップ、LOST AND FOUNDに行ってきました。
洋食器のNIKKOによる、日用品セレクトとショールーム併設の施設として11月にオープンしたそうです。 店内に入ると「忘れ物保管所」という名前にうなずける雰囲気の店内です。 テーブルまわりのものを中心に、知っている人にはあれもこれもどこかで見たことあるような、センスの良い友人宅にありそうなものばかり。(とても良い意味で!) その空間の奥に続く窯のようなスペースにNIKKOの食器が並んでいます。 百貨店に並ぶような食器たちが、倉庫のように棚に積まれているのが不思議な魅力です。 手前と奥の空間で照度が変わるのも面白いですね。 NIKKOのお店らしく品のあるセレクトは、決して派手ではないけれど、使えば分かる良さを持った日用品という感じで、ギフトにも良いですね。
リンク:LOST AND FOUND
新年あけましておめでとうございます。
謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
昨年も新型コロナウイルスの影響が続く中でしたが、
皆様には格別のご厚情を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
NIKKOのお店らしく品のあるセレクトは、決して派手ではないけれど、使えば分かる良さを持った日用品という感じで、ギフトにも良いですね。
リンク:LOST AND FOUND
新年あけましておめでとうございます。
謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
昨年も新型コロナウイルスの影響が続く中でしたが、
皆様には格別のご厚情を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
 仕事始めの日、デザインエイエムでは事務所近くの代々木八幡宮へ初詣に行きました。
長く続くコロナ禍ですが、近頃はワクチン接種や新薬開発により、
少しずつ改善の兆しが見えてきたように感じます。
デザインエイエムでは引き続き感染防止対策を徹底するとともに、
これまで以上に皆様のお手伝いができるよう励んでまいりますので、
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。持続可能な開発目標、SDGs。
みなさんも最近よく耳にすると思います。
世界規模でより良い社会にしていきましょうと銘打った17の目標…というのはなんとなく知っていても、具体的にどういうことをしていけば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
デザインエイエムでは、社内のSDGsへの意識を高めていこうと、SDGs17の目標すべてを達成している!という石坂産業株式会社の三富今昔村に社会科見学に行って参りました。
まず案内されたのは「くぬぎのもり環境塾」というちいさな講義室。
ここでSDGsの勉強と、石坂産業株式会社のビジョンを伺います。
仕事始めの日、デザインエイエムでは事務所近くの代々木八幡宮へ初詣に行きました。
長く続くコロナ禍ですが、近頃はワクチン接種や新薬開発により、
少しずつ改善の兆しが見えてきたように感じます。
デザインエイエムでは引き続き感染防止対策を徹底するとともに、
これまで以上に皆様のお手伝いができるよう励んでまいりますので、
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。持続可能な開発目標、SDGs。
みなさんも最近よく耳にすると思います。
世界規模でより良い社会にしていきましょうと銘打った17の目標…というのはなんとなく知っていても、具体的にどういうことをしていけば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
デザインエイエムでは、社内のSDGsへの意識を高めていこうと、SDGs17の目標すべてを達成している!という石坂産業株式会社の三富今昔村に社会科見学に行って参りました。
まず案内されたのは「くぬぎのもり環境塾」というちいさな講義室。
ここでSDGsの勉強と、石坂産業株式会社のビジョンを伺います。
 パンフレットと見学者用のパスをいただきました!
ダイオキシン対策を万全にしていたにもかかわらず、時代の流れから風評被害に翻弄されてきた石坂産業株式会社。
環境問題と地域社会との共生に正面から向き合い取り組みを続け、1万トンのゴミに埋もれた土地を希少植物も生息する豊かな里山に生まれ変わらせた現在までのお話や、今後のビジョンも含め伺いました。
国内そして世界の産業廃棄物リサイクル率についても学びます。
産業廃棄物が意外にも我々の身近にせまるゴミの問題だと、考えさせられます。
お話の中で、特に印象的だったのはSDGsのNo.12「つくる責任、つかう責任」に着目し、更に「すてる責任」まで考えて徹底的にリサイクルをするという企業姿勢。
石坂産業株式会社では、持ち込まれた産業廃棄物の98%が再資源化されるとのこと。驚きです。
さらに、ここで出していただいた狭山茶がとても香り高くて驚いたのはもとより、なんと湯呑もリサイクルされたもの。陶磁器がリサイクルできるなんて初めて知りました。真っ白で可愛らしい形からは想像できません。
パンフレットと見学者用のパスをいただきました!
ダイオキシン対策を万全にしていたにもかかわらず、時代の流れから風評被害に翻弄されてきた石坂産業株式会社。
環境問題と地域社会との共生に正面から向き合い取り組みを続け、1万トンのゴミに埋もれた土地を希少植物も生息する豊かな里山に生まれ変わらせた現在までのお話や、今後のビジョンも含め伺いました。
国内そして世界の産業廃棄物リサイクル率についても学びます。
産業廃棄物が意外にも我々の身近にせまるゴミの問題だと、考えさせられます。
お話の中で、特に印象的だったのはSDGsのNo.12「つくる責任、つかう責任」に着目し、更に「すてる責任」まで考えて徹底的にリサイクルをするという企業姿勢。
石坂産業株式会社では、持ち込まれた産業廃棄物の98%が再資源化されるとのこと。驚きです。
さらに、ここで出していただいた狭山茶がとても香り高くて驚いたのはもとより、なんと湯呑もリサイクルされたもの。陶磁器がリサイクルできるなんて初めて知りました。真っ白で可愛らしい形からは想像できません。
 三富今昔村のロゴマークがかわいいですね。底にはしっかりとエコマークが。
美味しいお茶と講義をうけ、SDGsの取り組みがすこしわかってきたところで、いざ工場見学へ。
随所で作業中の職員方の様子を見学しながら、作業内容の説明うけ進みます。
大きなブロック塀が最後は砂のように細かくなる様子は、大人でも感嘆の声が上がります。
三富今昔村のロゴマークがかわいいですね。底にはしっかりとエコマークが。
美味しいお茶と講義をうけ、SDGsの取り組みがすこしわかってきたところで、いざ工場見学へ。
随所で作業中の職員方の様子を見学しながら、作業内容の説明うけ進みます。
大きなブロック塀が最後は砂のように細かくなる様子は、大人でも感嘆の声が上がります。
 取り壊された住居の家具や柱などの木材の山。産業廃棄物って意外と身近なんだと感じさせられます。
取り壊された住居の家具や柱などの木材の山。産業廃棄物って意外と身近なんだと感じさせられます。
 選別され再利用された製品のサンプルも多数展示されています。
様々な工程を経て選別されますが、最後は手作業!
98%の再資源化を実現するため、徹底的な姿勢が伺えました。
選別され再利用された製品のサンプルも多数展示されています。
様々な工程を経て選別されますが、最後は手作業!
98%の再資源化を実現するため、徹底的な姿勢が伺えました。
 充分に工場見学で感動した後は、里山見学です。
本当にごみ処理施設の隣ですか?と疑いたくなるような豊かな緑に覆われた広場が広がっていました。
里山再生に対しても、再生資材を活用するだけでなく木々や植物の成長にあわせて、必要に応じた伐採することも含め取り組んでいるそう。
充分に工場見学で感動した後は、里山見学です。
本当にごみ処理施設の隣ですか?と疑いたくなるような豊かな緑に覆われた広場が広がっていました。
里山再生に対しても、再生資材を活用するだけでなく木々や植物の成長にあわせて、必要に応じた伐採することも含め取り組んでいるそう。
 施設内にはなんと養鶏場まで。生き生きと歩き回る姿がたくましいです。平飼いの卵は施設内のレストランの食事に使用されています。
施設内にはなんと養鶏場まで。生き生きと歩き回る姿がたくましいです。平飼いの卵は施設内のレストランの食事に使用されています。
 流通する「子芋」のために破棄される「親芋」を再利用したパウンドケーキと、施設内にあるしあわせ神社の絵馬をお土産にいただきました。
恥ずかしながら里芋が生産の過程で親芋が廃棄されることをしらず…こんなに活用できるのに!と驚きました。
三富今昔村レポートは「経営を強くするためのDESIGNAM MAGAZINE」でもたくさんのお写真とともにご紹介していますので、ぜひご覧ください。
→SDGsをもっと身近に!三富今昔村見学レポート
リンク:石坂産業株式会社 三富今昔村 公式WEBサイト
先日、当社で毎年恒例のX’mas & NEW YEARカードコンペを開催しました。
この時期がくると、もう今年が終わってしまう!という気持ちで少し焦ります(笑)
X’mas & NEW YEARカードは、毎年お世話になった皆さまへお送りしているカードで、
実はコンペにはデザイナー以外のスタッフも参加しています!
みんなの個性が表れるアイディアが発表され、多数決投票で1つの案に決定しています。
ちなみに過去のデザインはこちら
2020年Christmas & new yearカード
2019年Christmas & new yearカード
2018年Christmas & new yearカード
2017年Christmas & new yearカード
今年もたくさんのアイディア、聞くのが楽しかったです。
自分の作ってみたいとおもっていたものを落とし込んでみたり、時代に合わせたアイディアを出していたり…。
現在は、絶賛デザイン制作中です!
実際に決定した案は、年末ごろ皆さまへご案内予定です。
ぜひお楽しみに。
当社の働き方改革制度の1つ「ノー残業デー制度」をご紹介いたします。
ノー残業デーというと、会社全体で一斉定時退社のイメージが強いのでは。
当社の制度は、各自が自由に翌週のノー残業デーを決定して取得するというものです。
この制度は、残業時間を減らすというよりも、私生活とのバランスをとり生活にゆとりを持とう、という目的で作られました。
ちなみに…毎日1時間・週5で残業するのであれば、1日は残業しない日をつくり、別の日に2時間残業する日を作った方が生活にゆとりが生まれるという理論があるそうですよ。
ノー残業デーを取得するために、事前に翌週の仕事の確認・調整が必要になります。
仕事が忙しいと、どうしても目の前の仕事を片付けることに必死になってしまいがちですが、
時間的制約がある日を作ることで、時間の使い方を意識するトレーニングにもなっていると思います。
現在は週1回のノー残業デーですが、ゆくゆくは2回3回ともっと増やし、プライベート時間もより充実できる会社を目指しています。
皆さまの会社の制度も何かあれば、ぜひお聞かせください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
流通する「子芋」のために破棄される「親芋」を再利用したパウンドケーキと、施設内にあるしあわせ神社の絵馬をお土産にいただきました。
恥ずかしながら里芋が生産の過程で親芋が廃棄されることをしらず…こんなに活用できるのに!と驚きました。
三富今昔村レポートは「経営を強くするためのDESIGNAM MAGAZINE」でもたくさんのお写真とともにご紹介していますので、ぜひご覧ください。
→SDGsをもっと身近に!三富今昔村見学レポート
リンク:石坂産業株式会社 三富今昔村 公式WEBサイト
先日、当社で毎年恒例のX’mas & NEW YEARカードコンペを開催しました。
この時期がくると、もう今年が終わってしまう!という気持ちで少し焦ります(笑)
X’mas & NEW YEARカードは、毎年お世話になった皆さまへお送りしているカードで、
実はコンペにはデザイナー以外のスタッフも参加しています!
みんなの個性が表れるアイディアが発表され、多数決投票で1つの案に決定しています。
ちなみに過去のデザインはこちら
2020年Christmas & new yearカード
2019年Christmas & new yearカード
2018年Christmas & new yearカード
2017年Christmas & new yearカード
今年もたくさんのアイディア、聞くのが楽しかったです。
自分の作ってみたいとおもっていたものを落とし込んでみたり、時代に合わせたアイディアを出していたり…。
現在は、絶賛デザイン制作中です!
実際に決定した案は、年末ごろ皆さまへご案内予定です。
ぜひお楽しみに。
当社の働き方改革制度の1つ「ノー残業デー制度」をご紹介いたします。
ノー残業デーというと、会社全体で一斉定時退社のイメージが強いのでは。
当社の制度は、各自が自由に翌週のノー残業デーを決定して取得するというものです。
この制度は、残業時間を減らすというよりも、私生活とのバランスをとり生活にゆとりを持とう、という目的で作られました。
ちなみに…毎日1時間・週5で残業するのであれば、1日は残業しない日をつくり、別の日に2時間残業する日を作った方が生活にゆとりが生まれるという理論があるそうですよ。
ノー残業デーを取得するために、事前に翌週の仕事の確認・調整が必要になります。
仕事が忙しいと、どうしても目の前の仕事を片付けることに必死になってしまいがちですが、
時間的制約がある日を作ることで、時間の使い方を意識するトレーニングにもなっていると思います。
現在は週1回のノー残業デーですが、ゆくゆくは2回3回ともっと増やし、プライベート時間もより充実できる会社を目指しています。
皆さまの会社の制度も何かあれば、ぜひお聞かせください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter7 伝える
Lecture30 「共感」を得る3つのポイント
<POINT>
心をつかむプレゼンには“共感”が欠かせない。話し手が一生懸命語ること、外せないポイントを外さないこと、内容の深さを感じてもらうこと。この3つがポイントだ。
ポイント1 熱を込めて、自分の言葉で語る
最後に、「伝える」ためにポイントとなるのが「共感」です。
プレゼンの中には、会社の会議室で社長や部長を前にして、新企画を提案するもの、競合他社に交じってコンペスタイルで自社の案を発表するもの、社外メディアに対して新商品やサービスを発表する場合など、いろんなタイプがあります。
多くの場数を踏んだプレゼンの達人たちは、つい聞き惚れてしまうほど上手に話を展開し、最後まで飽きさせずに自分の持ち時間を終えます。
彼らのすばらしいプレゼンを聞くにつけ、「うまく話さなければ」「1回くらいウケなければ」「自信があるように見せなければ」と思いがちですが、仕事につなげるプレゼンは、そこまでのスキルはいりません。
大切なのは、まっすぐに相手の目を見て、自分の言葉で、一生懸命話すこと。それだけです。
カンペを読み上げるのではなく、きちんと前を向いて、聴衆の目を見て話す。そうすることで、本心から言葉を発している印象が強まります。あとは、オリジナルの魅力で勝負すればいい。立て板に水のような流暢さは必要ありません。
ぎくしゃくしようが、言葉に詰まろうがかまわない。慣れない場所で無理して笑いをとりにいくこともない。
ソツのない、言葉巧みな話し方よりも自分ならではのアイデアや考えを述べていくだけで十分です。
むしろ、ちょっとぎこちないくらいのほうが共感を呼んだり、応援されたり、愛されたりもします。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.213〜P.214
的確な内容だけでなく、真摯な姿勢が相手の心を打つんですね。
他にも、お客様に伝える時に難しい業界用語や横文字をなるべく使わず自分の言葉で伝えること、
相手の表情を見ながら伝えることも大切だと思います。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
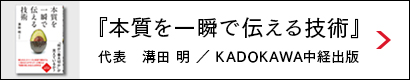 こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter7 伝える
Lecture28 信用を勝ち取るセルフ・ブランディング術
<POINT>
同じセリフでも言う人によって聞こえ方が変わる。発言が説得力を持つのは、言動や態度がブレないときだ。セルフ・ブランディングで“一貫性”という武器を身につけよう。
『人は見た目が9割』という話をご存じの方も多いでしょう。
これは、アルバート・メラビアンというアメリカの心理学者の実験に由来する“メラビアンの法則”をわかりやすくアレンジしたもの。ちゃんと本を読むと、9割はちょっと拡大解釈であることがわかるのですが、人が何かを判断する際、ビジュアルが多くのウェイトを占めているのは間違いありません。
「大事なのは内容でしょう!」と言いたくなりますが、ボサボサの頭で、小さい声で、まったく自信のない感じできょろきょろする人にプレゼンされたら、私でもちょっと発注をためらいます。
「この人は大丈夫だろう」「信頼できそうだ」と感じてもらえないと、内容すら見てもらえないのが正直なところなのです。
では、どんなふうにふるまえば、信頼してもらえるのでしょうか。
ばっちりスーツを着て、ソツのないネクタイを締めていればいいのか。それとも、ちょっと親しみやすい感じにするか。クリエイターっぽくオシャレに着崩した格好で臨むか……。
この問題に付随する頭の体操をしてみましょうか。ちょっと極端な例ですが……。
Q.私たちの目の前に、プレゼンテーションをしようとする2人の男性がいます。
年齢も背格好も変わりません。言っていることもほぼ同じ。
「私どもは、常に健康志向で、地球にやさしい会社を目指しています」
1人は、濃紺の麻のジャケットに白のパンツ。清潔感のあるシャツはノーネクタイ。髪は短め。手にはエコバッグ。
もう1人は、濃紺のピンストライプスーツ。髪は長く、後ろで束ねています。そして、はだけられた胸元にはネックレスがキラキラ。先の尖ったエナメルの革靴、鞄はいかにも高級そうなブランドバッグ、そしてタバコをぷかぷか。
この2人、あなたなら、どちらを信用しますか?
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.199〜P.201
五感の中で視覚情報が8〜9割を占めると言います。
よく「第一印象が大事」とも言いますし、見た目で人となりが一番に伝わってしまうので、
伝えたい印象(+自分らしさ)を自分でコントロールできるといいですね。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
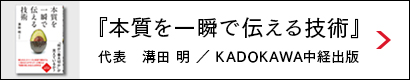 こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter6 直す
Lecture26 修正はファンを増やすチャンス
<POINT>
形になったからこそ、より具体的にシミュレーションができる。実際にモノが使われる現場に行って、検証の実験をしてみよう。きっと思わぬ発見があるはずだ。
「リセットする勇気」を持て
「どうもしっくりこないね」。
完成まであと一歩のところで、そんな意見が出てくることはまったくゼロではありません。
自分と相手、互いにモヤモヤしている。そんなときは、白紙に戻してやり直すこともあります。
徐々に軌道を修正するより、根本から見直したほうが早いことが多いのです。
そこまでの作業時間に1週間もかかっていたとしたら、到底受け入れることができないかもしれない。1か月、1年だったりすればもってのほかです。でも、そこまでの作業に1週間かかったからといって、根本に立ち戻ったときに完成までまた1週間かかって、産みの苦しみを味わうのかというと、案外そうではない。そこまでに考えてきた思考のルートやコツがすでにわかっているので、ロゴなどの場合もハマるデザインがすっとできたりします。
とはいえ、やっぱり緊張しますよね。時間は間に合うのか。報酬は作業時間に見合うのか。「前より悪くなった」なんて言われたらどうしよう。いろんな不安が胸をよぎります。そんなときは、ぜひ7Cの「吟味する」に立ち返りましょう。悪くなることなどあり得ません。正しく手をかければ、ちゃんとよくなるはずですから、心配しないでください。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.185〜P.186
根本的に方向性が違っている場合は90%の完成度のものをツメていくよりも、
一度土台から壊して方向性を修正し、そこから100%までツメる方が早い…
デザインにおいても往々にしてあることですね。
企画書や資料の作成などにも活かせるのではないでしょうか。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
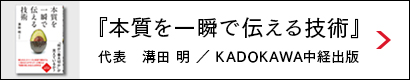 こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter6 直す
Lecture24 上司やクライアントの修正希望にどう応えるか?
<POINT>
なかなか素直に聞けない指示もあるが、つくったモノの最初の受け手となる彼らの言葉には真摯に耳を傾けたいところ。ケース別にベストな修正方法を考えてみよう。
さて、的を射た意見から不意なものまで、数々の指摘を受けたところで、どうするか。
社会人の経験を数年も経ると、我流の仕事術を身につけ、うまくいけば「あの人とはウマが合う」といい、イマイチかみ合わなければ「あの人とは相性が悪い」と言って嫌がります。さらに、こちらにはプライドもありますから、「この良さをわからないなんて、まったく……」という気持ちになって「もう、これでいいったらいいの!」と押し通したくなることも。
しかし、作家にとって編集者が最初の読者であるように、私たちにとっての上司やクライアントはモノを最初に見る受け手。その反応はぜひ参考にするべき、です。だから、まずは自分の気持ちやこだわりは捨て、真摯に提案を受け入れる姿勢で臨みましょう。応じたことで、相手の満足度も高まりますし、そうやって軌道修正したものは、まんざらでもないことが多いのです。一人で考えていたのではわからなかった意見によってますます感性が磨かれていきます。
とはいえ、彼らの希望にすべて従っていればOKかというと、決してそうじゃないのが難しいところ。クオリティを下げる意見が出てきたら、譲らない勇気も必要なのです。
つまり、修正の依頼がきたとき、まず考えるのは応じるべきか、戦うべきか。それが問題なのです。
もちろん、なかには、「そこを変えたら全部変えなきゃダメだ!」というヘビーな修正依頼が入ることもあるでしょう。「徹夜が水の泡!? 絶対いやだ。説得しよう」 なんて気持ちになることもあるかもしれません。でも、ここで「戦う」ことを選ぶのはちょっと違う。戦うのは、あくまでもクオリティを下げないためです。
また、言われてすぐ「でも」「いや、それはちょっと」とすぐに反論しても仕方ないので、まずは7Cの「よく見る」「受け止める」の術を駆使して相手の話をすべて聞くなどの技術が必要なのです。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.168〜P.170
感情的な思考は、論理的な思考を邪魔することが多いですよね。
まずはクライアントの想いを素直に聞き入れた上で、論理的に取捨選択できると良さそうです。
私も日頃から気をつけたいと思います!
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。
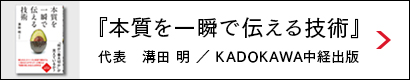 企業には、理念(事業・計画などの根底にある根本的な考え方)、それに紐づくビジョン(展望)、ミッション「誰に対して何をなすべきか」といったものがあります。
商品やサービスであれば、<理念>ほど大袈裟なものではなくても、「社会や生活者にとってどのような意味や意義をもっているのか」というコンセプトのようなものかもしれません。
コロナ禍の中、この大義はますます求められてくる傾向にあると言えるかもしれません。
なぜならばそれが他社との差別化にもつながるからです。
この<理念>について改めて考えてみたことはあるでしょうか。
「大手企業のもので中小企業や小さな事業にはあまり関係ないのではないか」
「理念が大切だと言われているのは知っているけれど、なかなか真剣に考えるまでには至っていない」
時には「確かあったけれど何だっけ・・・・?」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私自身は、大学院でMBA(経営学修士)のエッセンスを学ぶようになり
さまざまな企業の事例を目にする機会が増え、この企業理念に対する見方が大きく変わりました。
なぜならば企業として、従業員として、仕事に取り組む上で指針となるからです。
そこに企業の大小は関係なく、ひとりひとりの仕事に向かう姿勢に変わりはないからです。
こんなお話しをきいたことがあるでしょうか。
理念やビジョンが大切だという象徴のような例え話しです。
企業には、理念(事業・計画などの根底にある根本的な考え方)、それに紐づくビジョン(展望)、ミッション「誰に対して何をなすべきか」といったものがあります。
商品やサービスであれば、<理念>ほど大袈裟なものではなくても、「社会や生活者にとってどのような意味や意義をもっているのか」というコンセプトのようなものかもしれません。
コロナ禍の中、この大義はますます求められてくる傾向にあると言えるかもしれません。
なぜならばそれが他社との差別化にもつながるからです。
この<理念>について改めて考えてみたことはあるでしょうか。
「大手企業のもので中小企業や小さな事業にはあまり関係ないのではないか」
「理念が大切だと言われているのは知っているけれど、なかなか真剣に考えるまでには至っていない」
時には「確かあったけれど何だっけ・・・・?」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私自身は、大学院でMBA(経営学修士)のエッセンスを学ぶようになり
さまざまな企業の事例を目にする機会が増え、この企業理念に対する見方が大きく変わりました。
なぜならば企業として、従業員として、仕事に取り組む上で指針となるからです。
そこに企業の大小は関係なく、ひとりひとりの仕事に向かう姿勢に変わりはないからです。
こんなお話しをきいたことがあるでしょうか。
理念やビジョンが大切だという象徴のような例え話しです。
旅人がある町を歩いていると、石垣を積んでいる職人3人と出会いました。
旅人は、1人目の職人に「何をしているのか」尋ねると、
職人は「見ればわかるだろう。飯を食うために石を積んでいるんだよ。」とぶっきらぼうに答えた。
旅人は、2人目の職人にも尋ねた。
「石垣を積んでお城を造っているんだよ。よくわからないが立派な城らしい」と答えた。
旅人は、3人目の職人にも同じ質問をしてみた。
「石垣を積んで立派なお城を造っているんだ。この国の人々が未来永劫平和に暮らせる世の中になるためのお城づくりの一役を担っているのさ。」と答えた。
仕上がりは3人目の職人の完成度が一番高かったことは言うまでもありません。
同じ仕事でも「どんな理念・ビジョンで仕事をするのか」によって
モチベーションや結果に差が出てくるということです。
「石垣を積むだけ」の職人よりも
「この国の人々が未来永劫平和に暮らせる世の中になるため」に働く職人に、
大多数の方は依頼したいと思うのではないでしょうか。
そして共に働く仲間と理念を共有する。心をひとつにして仕事に臨む。
また、社外に理念やビジョンを発信していくことは大切です。
共感していただくことができれば、単なる購入者ではなく、ファン即ち応援をしてもらうことに繋がるのです。
またこの理念をもとに、新規事業を検討する際なども業務内容を精査する軸になるかと思います。
より理解を深めるために、いくつかの企業理念の事例をみていきましょう。
●スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
ミッション:
「人々の心を豊かで活力あるものにするために
-ひとりのお客様、一杯のコーヒー、そしてひとつのコミュニティから」
<参考>
https://www.starbucks.co.jp/company/mission.html
●ハーゲンダッツジャパン
わたしたちは、「お客様の期待を超えるフローズンデザートを提供することにより、
お客様に喜びと感動(ハーゲンダッツ・モーメント)を提供し続ける」ことを使命として企業活動を行っています。
そのための哲学ともいえる企業理念が「Dedicated to Perfection(完璧を目指す)」です。
<参考>
https://www.haagen-dazs.co.jp/company/csr/compliance.html
それぞれの企業が成長し続けている理由がわかる気がしますね。
ぜひご自分の会社の企業理念に着目してみてください。
もし現在あるならば、方向性の確認、点検を。なければこれを機に考えてみてはいかがでしょうか。
そして継続して社内に浸透させることを忘れずに・・・。
(社内浸透については次回ご紹介します)
また他の企業やお店の理念を調べてみると新たな魅力の発見になるかもしれませんよ。
【TEXT / ATSUKO MURAKAMI(director)】こちらの特集では、弊社代表の溝田 明による著書
『本質を一瞬で伝える技術』を一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。
見えにくい本質をつかみ、一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた
デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。
ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、
皆さまのビジネスにお役立てください。
Chapter5 吟味する
Lecture21 他人の頭になって見直す
<POINT>
1つのことについて考え尽くしたとき、私たちは誰よりも詳しくなっている。そして客観性を失う。時間をおいて、もう一度詳しくなかった頃の自分を取り戻す。
「受ける印象」と「キーワード」の答え合わせをする
目指すものが完成したら、まずはその場から離れましょう。
パソコンで作業していたのなら、席を立って。カフェに行ったり、散歩したり、運動したり、映画を観たり。徹夜続きで疲れているなら、まっすぐベッドへ。時間がないなら、5分でもかまいません。風にあたったり、歩いたりして熱くなった頭を冷やします。あるいは別の仕事をするのも手です。
なぜか?
ここまでにじっくり対象を観察し、多くのアイデアを出し、それについて考えつくしたつくり手は、いわばツウです。もはやマニアといってもいい状態。 何も知らない人の視点からはかけ離れています。
そこで、つくったものと距離をとることで、自分がつくり手であることを一時的に忘れるのです。かけた時間も、こだわりも、愛着もすべて忘れ、ゼロに。
そして、届けたい相手の目線になりきったとき、いろんなことができるようになります。
たとえば、「答え合わせ」もその1つ。
つくったものを改めて見返したときに、自分が意図したキーワードを感じられるかどうか。たとえば、ロゴで自分が意図したものが、ちゃんと伝わっているかどうかをチェックできるのです。
著:溝田 明『本質を一瞬で伝える技術』 P.151〜P.152
新しい企画やデザインをする時のあるあるですね…!
客観的に考えられるよう、一旦離れて思考を変えてみる試みはとても良いですよね。
可能であれば、内容を全く知らない人に客観的な意見をもらっても良いかもしれません。
今回取り上げたチャプターの全文や、
その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。